◆作家の収入
他人の懐具合を探るのは好い趣味ではないが、他方では、パンのみにて生きるにあらずともいい……。本人が生きておられたら、さしずめプライバシーなのだが、著名人の弱み……。そこはそこ、作家の実像を知るという正当化のもとに、いささかの詮索をしようという次第。
1.綺堂の収入
1−1.新聞記者としての収入
野崎左文『私の見た明治文壇』(春陽堂、1927.5.15)の「明治初期の新聞小説」によれば、おそらく、明治27‐8年頃のことと思われるが、小説記者の収入が、おおよそ12‐3円、最高で24−5円までの間であったとしている。小説記者がどの程度の仕事をするものかわからないが。
野崎左文は1858(安政5)年生まれだが、1874(明治7)年の末、品川の工部省工作局(硝子製造所)に勤務だった20歳前で、工部8等技手で月俸20円だった。が、1880(明治13)年、仮名垣魯文の仮名読新聞へ入社して、俸給は15円になったが、この額でも、社中の人には高すぎるという苦情が出たらしい。
当時白米が1円で1斗4‐5升で、借家でも5‐6円だせば玄関付きの立派な家が借りられたという。また、月給以外に、他人の代作とか地方新聞の続物を書くとか、新聞に発表した小説を今度は単行本として書店から出すなどすれば、優に一家の生計を支えることができたという(同38−39頁)。
綺堂の場合
明治24年頃、日日新聞社から15円の月給を貰っていた。綺堂19歳頃である。岡本綺堂・明治の演劇126頁(大東選書)。綺堂の好物であった、その頃の竹葉の蒲焼が12銭5厘、飯が3銭(いずれも一人前)であった。駈けだしの記者であったことを考えれば、15円の俸給は立派なものといえるのではなかろうか。
永井荷風の場合
明治34年頃、やまと新聞に雑報記者として入社したが、月給は12円だったという。
荷風随筆集下巻82頁(岩波文庫、1986)
・新聞記者でも、編集長クラスになるとむろんもっと収入があった。
先ほどの野崎左文は仮名垣魯文の門下だが、彼によると、仮名垣魯文は、「仮名読新聞」に入社したときには40円(月額)、明治13年いろは新聞に入ったときが50円、同17年今日新聞に入社したときが75円であった。
明治10年頃の40円は、「中流の生活費としては裕(ゆた)かなもの」(野崎・28頁)であったという。また、自作の著述や序跋文を書いたりなどサイドビジネスもできたらしく、それをあわせると倍にはなったとしている。
福地源一郎(桜痴)は、征韓論で外務省を下るが、東京日日新聞の社長となったとき(野崎は明治6年としている)、その俸給が100円と聞いて、人々は驚異の眼を光らせたほどだったという。事実とすれば、むゝ、かなり高額ですね。
福地は下戸で謹厳だったそうだが、吉原で通客として浮名を流したこともある。なんでもてるのかというやっかみ記事もあるが、この収入のせいでしょうか、否、明治男の心意気なのでしょうか。
塚原渋柿園の場合
渋柿園氏は、明治11年東京日日新聞社入社で、岡本綺堂の先輩格にあたり、綺堂は、芝居や江戸のことなどを彼に教わった。同社での渋柿園氏の立場がわからないが、明治19年までは月給80円であったが、『報知新聞』の値下げのため、それへの対抗上、俸給も減額されたらしい。そこで70円になったという。ちなみにこのとき、東日の社長の福地桜痴も、それまでの250円から200円になった。大塚豊子「塚原渋柿園」近代文学研究叢書17巻222頁(1961年)。
ジャーナリストも当時も忙しかったらしいし、また、東京日日新聞などいわゆる大新聞と小新聞とでは条件も違ったであろうが、一説によると小新聞の方がかえって発行部数も多く売上も大新聞よりよかったという。いずれにしても、一般に、記者としての収入はよく、大体中流くらいであったといえよう(前記、野崎左文)。むろん、石川啄木(当時、東京朝日新聞の校正記者)のような例(外)もあるが、新聞記者は裕福な方であったようだ。
1−2.劇作家としての収入
大正15年以降の頃
大正15年以降の話のようだが、岡本綺堂の小遣は、月に100円だったという。これで洋書などの書籍を購入したり、弟子たちとの小旅行(わかば会の宿泊代など)などに使ったという。岸井良衛・ひとつの劇界放浪記。岡本綺堂が全盛の頃だと言ってよいだろう。 岡本家は、子どもはないものの、女中さん2人を置き、書生さんを高校に通わせるという、5人の所帯であった。
岡本綺堂、昭和初期
当時の上演料としては、初演の場合、1幕物で250円、1幕を加える毎に100円増しであったという。つまり、3幕物だと450円となる。それ以前はもっと安かったようだが、松竹の取決めであるという。再演となると、半額となったようだ。岸井良衛・一つの劇界放浪記59頁。
綺堂の場合は、総てこれが手元に残るというのではなく、このうちから、いく方へ祝儀として渡していたようである。同上。
1−3.演劇界、ことに歌舞伎界
「市川団十郎、億万長者」
今日だったら、さしずめこのような記事が載るところ、である。9世市川団十郎は、日本一の高収入だったという記事がある。
明治座の岡鬼太郎
岡鬼太郎が、綺堂の友人の記者仲間、芝居仲間であることはすでに記した(「綺堂の友人たち」「明治の演劇小史」)。初代左団次と古くから組み、またその息子の2世左団次の芝居上の後見人あるいは相談役とでもいうべき、劇作家でもある松居松翁(綺堂もかつて記者仲間で机を並べたことがある友人でもある)が明治座と深い関係を持ってきたことから、松居から誘われて、新聞記者の鬼太郎は記者を辞め、明治座の芝居の「演出」(当時、まだ「演出」家という言葉はなかった)みたいな役を担当することになった。
そのときの、岡鬼太郎の給料が260円だったらしいという話を自らしている。本人がして「らしい」というのは変だが、いくらとは自ら明らかにしていない、260円だろうと知合いの記者に訊ねられたという話をしている。明治39年の、明治座の改革興行の直前の話で、岡鬼太郎が35歳の頃のエピソードである。これが本当なら、芝居系の方が新聞記者よりもより収入は高いといえようか。ただし、座の浮沈・人気との兼ね合いがあってつねにというわけにはいかなかっただろう。
2.他の作家たちとの比較
2−1.夏目漱石
漱石は、明治40年、帝大文科大学講師および一高教授を辞し、東京朝日新聞に入社する。そのときに、契約を交わしたことが、当時としては異例でもあったのか、漱石のげんきんさないしは西洋的合理性を示したものかという話題ともなった。
さて「民間」への転出前はどうだったのだろうか。鏡子夫人の記憶によると、明治36年4月、帝大文科大学講師で800円年俸、一高教授で700円年俸(兼任だったようですね)、明治大学が月30円(こちらはアルバイト先ですね)が固定で、あとは臨時の原稿料とか印税があったようだ(夏目鏡子述『漱石の思い出』(1994、文春文庫)187頁)。
これらを月に換算すると、約67+約58+30=155円+α(原稿料他)ということになるが、主婦の立場としては、月にどうしても200円はかかると言っている。帝大教授(専任)になると月150円になったそうだが、漱石はこの道を取らなかった。
明治40年4月に入社した東京朝日新聞との契約は、俸給200円(月あたり)+賞与、を給するというものであったが、朝日専属で、年に小説を何本とか記事をいくつとか書くという内容だった。帝大のときのように恩給(いまでいう年金)が付かないから、賞与を少しづつ上げていくやり方だったらしい。単純に俸給面だけで見れば、民間へ転出つまりプロ作家の方が上だということになる。東京朝日に知合いが居り、そちらからの申出ないしは引抜きだったという事情もあるようだ。
ちなみに、漱石は、松山中学教員時代には月俸80円(明治28年)を貰っていた(古川久編「注解」漱石全集3巻358頁(1979第7刷、岩波書店))。なお、小説『坊ちゃん』の本文第一節ではなぜか「40円」として半額にしてある。
続いて、熊本五高教授時代(明治29年4月ー)には、月俸100円となっている。東京に帰った後は、上に書いた次第。ただ、高等学校の収入にだけ限ってみると、五高時代の月俸100円と一高での年俸700円(月額に直すと約58円)とでは、減額のようだが、帝大講師との兼任による“調整”があったためだろうか?
3.原稿料
3−1.明治20年代
二葉亭四迷
二葉亭こと長谷川辰之助は、明治20年6月、金港堂より、坪内逍遥の肝煎りのもと、かの『浮雲』第一編を世に出した。表紙は、坪内博士の名義である。二葉亭と坪内博士は押し問答の末、80円の原稿料のうち、35円を坪内、45円を二葉亭が取ることになった。二葉亭のたっての要望を、坪内博士が聞き入れたという次第である。二葉亭は、このとき24歳である(中村光夫『二葉亭四迷伝』(講談社文芸文庫、1993)146頁参照)。
二葉亭は、このとき24歳である。
田山花袋と樋口一葉
貧困の中の作家として挙げるならば、樋口一葉を外せない。父がまだ官吏だった頃は羽振りもよくて生活には困らなかったが、稼ぎ手の死亡とともに生活の困窮が押し寄せてきた。恋人でもあり、文学上の相談相手でもあった作家の半井桃水にすら借金を申し込まざるを得なかった。
田山花袋『東京の三十年』(岩波文庫、1981)によると、
『都の花』明治25年11月号には、田山花袋の最初の原稿「新桜川」(田山「花岱」とある)とともに、樋口一葉の処女作『うもれ木』も掲載されたのである。田山は、日本橋の金港堂書店(日本橋区本町3丁目17番地)の応接間で「一枚三十銭の割で七円五十銭私に渡した」(同書64頁)とある。まだ無名の駆け出しの作家である時期で、これが花袋の最初の原稿料だった。
ちなみに、一葉のその時の稿料は、むろん原稿の枚数が違うが、11円15銭だった(森まゆみ『一葉の四季』(岩波新書、2001)36頁)。この原稿料で、一葉一家母子3人はなんとか一ヶ月は暮らすことができた。ちなみに、塩田良平『樋口一葉研究』(後掲)410頁によると、「うもれ木」の時期の樋口一家(母、一葉、妹邦子)は「月、10円以内で十分暮せたはずである」としている。 翌年、有名な、竜泉寺町に引越しするが、敷金が3円、家賃が1円50銭だったという(森まゆみ『一葉の四季』38、114頁)。
一葉の日記の、明治26年2月6日の項に、
- 「我は営利の為に筆をとるか。さらば何が故かくまでにおもひをこらす。得る所は文字の数四百をもて三十銭にあたひせんのみ」
『一葉全集 第3巻』(筑摩書房、1954.6.16)271―272頁
一家を自分の筆で支えていくことを余儀なくされた、そしてプロ作家としての出発する覚悟の時期の感慨のようである。
いくつかの点で疑問が残る。
一つは、「うもれ木」の稿料である。塩田良平『樋口一葉研究』(中央公論社、昭和31年10月発行)によると、「うもれ木」(『都の花』95号2頁、明治25年11月20日発行、金港堂の刊行雑誌)の「稿料は一枚二十五銭といふことになった。」(同411頁)。そして、明治25年10月「22日、猿楽町に藤蔭を訪ねて11円75銭を受け取った。」(413頁)とある。藤蔭とは、『都の花』の主幹である。24日には、『都の花』への寄稿を斡旋してくれ、紹介文を書いてもらった三宅花圃のもとへ礼に行っている。ただ、森まゆみの記述「11円15銭」の稿料という数字が違う。
もう一つは、明治26年2月6日の日記の記述がどの作品の後のものであるかという点である。明治25年12月27日の日記によると、「うもれ木」の次の作品である「「暁月夜」三十八枚分十一円四〇銭を本両替町の金港堂で藤蔭から受けとった。」(塩田・424頁)。ただし、受けとったのは翌28日午前中である。これは1枚当たり30銭で計算されている。
さらに、一葉は、「暁月夜」の次の作品を、明治26年1月20日に「雪の日」脱稿しているが、これは3月31日、『文学界』3号に発表された。ただし、前記塩田によると、「この稿料はいつ払われたか不明。日記は筆墨料(日記二六・二・二六)としか記録されていない。」(塩田・430頁)としている。
とすると、2月6日の日記の記述は、「うもれ木」でもなく、「雪の日」の稿料が入った後でもないようだ。当時の一流誌『都の花』で実質的な文壇デビューを果たし、その後の作品も評価はとまれ、営利職業作家の仕事振りも順調と見えるのに、上に引用した2月6日の記述は、まだ逡巡を感じさせるものがあるが、どうだろうか。なお、原稿買取制のためだろうが、今日とは違って、雑誌の刊行前に稿料が支払われていたというのも面白い。
なお、一葉の「たけくらべ」の原稿の写真を見たが、現在の四百字詰め原稿用紙と変らない体裁で、縦20字X横20字で、ただルビを振るスペースが行間にないマス目式のものである。おそらく市販のものであったあろう。この時期に、四百字詰め原稿用紙が存在していたことも余談ながら興味深い。
3−2.明治30年代後半
夏目の場合
もう一度夏目漱石に登場してもらおう。江戸っ子だから金銭には無頓着だった?が、―でも『坊ちゃん』作中での、俺と山嵐の、職員室での5銭だったか10銭だったかのやりとりはすさまじいものがあったが、あれはもう銭を超えて意地になったのですね―、そのために原稿料や印税には無頓着でいくら貰ったかも知らなかったらしい。そこで、鏡子夫人の叙述による。
「カーライル博物館」が全体で8円、雑誌「ホトトギス」が1枚50銭、のち1円に上がった。雑誌「新小説」が1円くらいで、雑誌「中央公論」が1円20‐30銭であったという(夏目鏡子・前掲書175頁)。
この「1枚」というのが、原稿用紙あたりなのか、印刷出来ページあたりなのかよくわからない。鏡子夫人が漱石が書きあげた原稿を1枚1枚数えたとも考えられないが、出版社の方で○枚の原稿用紙があったのでそれに単価を書きつけたものとともに原稿料を送ってきたものか…?
『二葉亭四迷伝』の著者中村光夫氏によると、当時の出版契約は、印税計算ではなく、現行の買切り制であったことを明らかにしている(同(講談社文芸文庫、1993)・146頁)。したがって、その後に再版がなされたとしても、最初の買い切りの値段で終わりである。再版や再三版によって売れれば売れるほど出版社の懐には入ることになり、作家にとっては、ちょっと酷な気がする。それはさておき、買い切り制ならば、原稿1枚あたりいくらという計算になろうか。鏡子夫人や一葉らが一枚いくらと云っているのは、十分の根拠があるわけである。
ちなみに「カーライル博物館」は1905(明治38)年1月号『学燈』誌上、また「我輩は猫である」は「ホトトギス」誌上に明治38〜39年にかけて発表された。なおこの時期に、「新小説」と言っているのは「草枕」(明治39年9月)、「中央公論」というのは「薤露行」の発表(明治38年11月)を指していると思われる。
3−3.岡本綺堂 大正以降
新聞記者を辞めた後は、作家生活である。文字通り筆一本で一家を支えなければならない。 月々の連載物、臨時の原稿など、劇作以外にも、原稿を書かなければならない。日記にはどの社や雑誌から原稿料が送ってきたと記録してあるが、その額までは記してない。このあたりが、明治人の奥ゆかしさというべきか。それで、この記事も目下のところは、ここで頓挫する。
第三者による評判記事があることが分かりましたので、ご厚意により掲げます。
御入力また同ファイルを提供され、ここでの公開を御快諾下さった石瀧様には感謝申し上げます。(5/15/2006)
| 高橋孤川 「現代百生活 文筆成金評判記 ―現代文士の収入調査、成金と言つても知れたもの―」 『日本一』第4巻第2号(大正7年2月1日発行) 「 家作持ちの岡本綺堂君 坪内逍遙博士、森鴎外博士なども成金とまでは言へないかも知れないが又、定収入と位置があつて、文筆に携つてゐた人達ではあるが、相当に貯つてゐることは推察する事が出来る。岡本綺堂君の如きも、家作を持つ位は貯つてゐるやうだ。尤もこの人は、父祖の産がある上に、普通(なみ)ならぬ稼手(かせぎて)であるから、脚本、通俗小説の両刀使ひを、精々(せつせ)とやりつゝある。殊に脚本料が可成りの収入を為してゐると見なければなるまい。 通俗物で当てた幹彦君 霞亭君と並び称される人に、若手で、長田幹彦君がある。幹彦君も、世間で徒らに驚いてゐるほどの多作家ではないが、それでも、一時に、新聞小説を三個所も引受けて、別に雑誌に三つ平均位は書いてゐられる男だから、まづ霞亭君と綺堂君との間に坐るべき達者な人と言はれよう。新聞の続物は、一回分の原稿料が五円から七円迄、時に十円のこともあるから、この三者の収入は想像がつくことであらう。昨秋あたりは幹彦君一ヶ月の収入は約三百円と謂はれて居た。それに、この人達の多くは、雑誌にも、連続物を書いてゐるからお座敷は絶え間なしに、勤めてゐることになる。同時に、之れ等の作物(さくもの)が、小説集になつたり、単行本にされたりして、一ヶ月一冊平均とまでゆかずとも、それに近い位、出版されるから、それから上る印税をも加算して、この三人者(にんしゃ)は、その働き振りも目ざましいが、小成金として許されるだけの収入もあるわけである。だが、綺堂君のは、筆は、速い方ではない。まめな方なのだ。」 公開:2006年5月15日 入力+ご提供:石瀧豊美@イシタキ人権学研究所 様 |
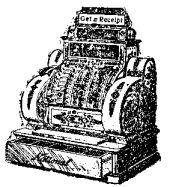
キャッシュ・ドゥローワー 大正期の新聞広告より
