岡本綺堂自身によると、江戸のことや芝居について多くの教えを受けた人達として、塚原渋柿園、條野採菊、西田菫坡の名を挙げている。いずれも、新聞記者時代の先達・知り合いである。
ここでは、これらの人たちに加えて、岡本綺堂の人生の中で転機となった人達を挙げて、綺堂の師と呼ぶことにして、つぎにこれを掲げた。
◆塚原渋柿園 (1848・嘉永元年―1917)
 本名、塚原靖(しずむ)。元幕臣旗本で、20歳で明治維新を体験し、慶喜の駿河移封に伴って、静岡で辛酸生活を送る。横浜毎日新聞の編集者であった頃、同社の仮名垣魯文の影響を受けたが、明治8年10月、新聞紙条例(明治8年6月発布)に違反して、罰金・禁獄。成島柳北は、慰めるため、酒樽を置いて帰ったという。
本名、塚原靖(しずむ)。元幕臣旗本で、20歳で明治維新を体験し、慶喜の駿河移封に伴って、静岡で辛酸生活を送る。横浜毎日新聞の編集者であった頃、同社の仮名垣魯文の影響を受けたが、明治8年10月、新聞紙条例(明治8年6月発布)に違反して、罰金・禁獄。成島柳北は、慰めるため、酒樽を置いて帰ったという。明治11年、福地桜痴の勧めで、東京日日新聞社へ入社した。劇評などを担当。19年頃から本格的に著作をはじめる。初期の翻訳「昆太利物語」(ビーコンスフィールド)は北村透谷らに影響を与えた。
また明治25年頃からは、一貫した歴史小説家として活躍する。史実について丹念な考証の上に立った、武士道モラルの意識や行動を描き上げたものが多い。代表作に『由井正雪』『天草一揆』などがある。「渋柿」「自由思」「柿叟」などの号を用いた。
しかし、綺堂が入社した明治23年1月頃には、劇評のための芝居見物を面倒くさがって、劇評は新入りの綺堂少年(当時17歳)に譲ることになったらしい。渋柿園41歳の頃であり、社会小説「条約改正」を「東京日日新聞」に連載中であったことなどで歌舞伎の方に目が向いていなかったものと思われる。
また、渋柿園は、狂言綺語からとった「綺堂」の名付け親でもある。当初は「狂綺堂(主人)」などとしていたが、読者から間違えて「狂気堂」とする手紙などが届くため、いっそ「綺堂」にしたという。
半七捕物帳にも登場
塚原自由思(渋柿園)は、綺堂の半七捕物帳にも登場する。半七老人と知り合いの新聞記者の青年は、渋柿園と知己の間柄であったという設定になっている。
「歴史小説の老大家T先生を赤坂のお宅に訪問して、江戸のむかしのお話しをいろいろ伺ったので、わたしは又かの半七老人にも会いたくなった。」 ―「勘平の死」
このT先生というのが、塚原渋柿園(がモデル)といわれている。
「赤坂のお宅」
ただ、今井金吾氏は、明治36年頃の渋柿園の住居は、麹町5丁目(当時。現在の麹町8丁目)の南端あたり(で、道路を隔てて紀尾井町と接している)にあって、(聞き役の記者の青年が)赤坂から弁慶橋を渡って麹町5丁目(現、8丁目)の渋柿園の宅へ来たから、「広い意味で『赤坂のお宅』と表現したのだろう」としている(岡本綺堂『半七捕物帳巻の一』(筑摩書房、1998)92頁「註解」)。あくまでも、弁慶橋から見えた(旧)麹町5丁目の洋館(であったことは、確認されている)を訪問したとするようである。しかし、この推測は当っていない。
実は、「(渋柿園の家が)麹町紀尾井町九番であったから赤坂と書いたのだろう」とするのは、今井氏だけではなく、木村毅氏もそうである。どうやらこのあたりから、紀尾井町だがその近くの赤坂とする説が生まれたものらしい。いずれにしても正しくない。(この一文、2001年4月16日追加)
渋柿園は、この麹町5丁目(紀尾井町に接する)の洋館から、実は、その後、赤坂仲之町の武家屋敷跡に転居しているのである。「仲之町」は、現在の、TBSの南側、地下鉄千代田線赤坂駅の南あたりで、現赤坂6丁目に含まれている。孫の鈴木千枝雄氏の文章によると「仲之町の家も、かなり豪奢だった。冠木門があり、…大名屋敷のように大玄関があり、小さい玄関が其の傍らにならんであった」という。乃木希典将軍が来訪し、また渋柿園が2階に引きこもって執筆に集中する余り、三年も女中の顔を見たことがない奇人だと言われた(阪井弁「明治畸人伝」(明治36年5月))のはこの頃である。また、渋柿園の「桜痴居士」と題する記事では、「赤坂中の町の寓居において」と自ら記している(ただし、「仲」は「中」となっている。江戸期の地図でも、中の丁としている。太陽18巻9号188−196頁(明治45年6月15日))。このように、綺堂が「T先生を赤坂のお宅」に訪ねたと書いたのは、正確であるといえよう。
半七親分は渋柿園の歴史小説が好き
また、半七老人自身も、渋柿園の歴史小説を新聞の連載で読むのが好きだとある。
「これは明治30年の秋と記憶している。十月はじめの日曜日の朝、わたしが例によって半七老人を訪問すると、老人は六畳の座敷の縁側に近いところに座って、東京日日新聞を読んでいた。老人は歴史小説が好きで、先月から連載中の塚原渋柿園氏作の『由井正雪』を愛読しているというのである。」
(半七)「渋柿園先生の書き方はなかなかむずかしいんですが、読みつづけているとどうにか判ります。…」 ―「正雪の絵馬」
渋柿園の年譜によると、傑作との評価の高い「由井正雪」は、明治30年9月から翌年の7月まで連載されているので、綺堂の記憶に間違いはない。また、綺堂の、渋柿園の小説についての感想が出ているようで興味深い。なるほど、渋柿園の小説は、漢字が多いためか、今日から見ると取っ付きにくい。
塚原邸の前を通りかかった乃木希典が「おじいさんのように偉い人になりなさいよ」と頭を撫でた、孫の鈴木千枝雄は、役人の傍ら、綺堂の門下となっている。
渋柿園の詳しい経歴と作品については、
塚原渋柿園(自由思園)の歴史小説のページ、参照。
◆條野採菊 (1832・天保3−1902・明治35)
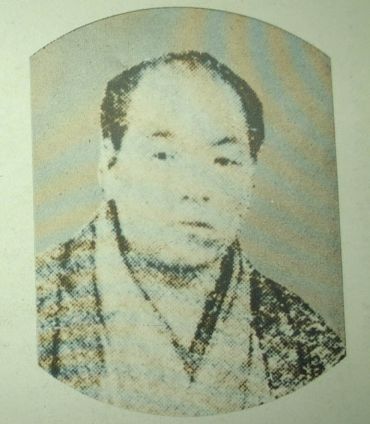 山々亭有人(さんさんてい ありんど)、「條野有人」「條野採菊」などとも称したが、本名は條野伝平。日本橋長谷川町の地本問屋の生まれで、本郷三丁目の呉服屋伊豆蔵の番頭を勤めるかたわら、幕末江戸時代から、仮名垣魯文とともに「春色恋廼染分解(しゅんしょくこいのそめわけ)」などの戯作を執筆した。
山々亭有人(さんさんてい ありんど)、「條野有人」「條野採菊」などとも称したが、本名は條野伝平。日本橋長谷川町の地本問屋の生まれで、本郷三丁目の呉服屋伊豆蔵の番頭を勤めるかたわら、幕末江戸時代から、仮名垣魯文とともに「春色恋廼染分解(しゅんしょくこいのそめわけ)」などの戯作を執筆した。西田菫坡や落合芳幾らとともに東京日日新聞社の創立者の一人である。また、東京絵入新聞にも関係した。明治17年10月には「警察新報」を創刊したが、これを明治19年10月には「やまと新聞」と改めて、主宰した。須藤南翠、饗庭篁村らとともに、明治20年代の新聞社派の劇作家である。福地桜痴から材料を得て翻案小説も執筆し、歌舞伎座の創設にも協力した。
また、主な劇作品としてつぎのものがある。
明治22年11月 「千金の涙」『歌舞伎新報』
30年2月 「並江戸子」(伊井蓉峰のため書き下ろし・宮戸座上演)
30年9月 「依田の苗代」『太陽』
32年11月 「森の小鏡」『やまと新聞』
このほか、ペリーの浦賀来港以降の近世の歴史を詳細につづった『近世紀聞』の著書がある。
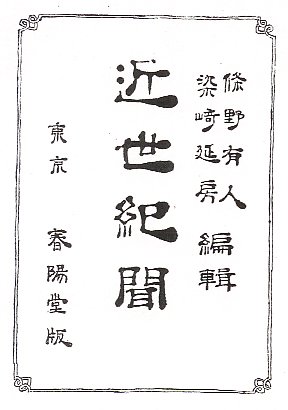
明治になって、採菊翁が、やまと新聞勤務のときに、青年岡本綺堂と出会っている。同じ編集室で、机を並べたこともあった。採菊老人は、日本画家である鏑木清方の父である。綺堂と清方とは、若い時代は、芝居見物に行く仲であったらしい。
・條野採菊のページ 自家メモ版 採菊の人となりと業績などの紹介
右の画像は、復刻による春陽堂版(大正15年10月刊)
◆西田菫坡 (1838・天保9 ― 1910・明治43)
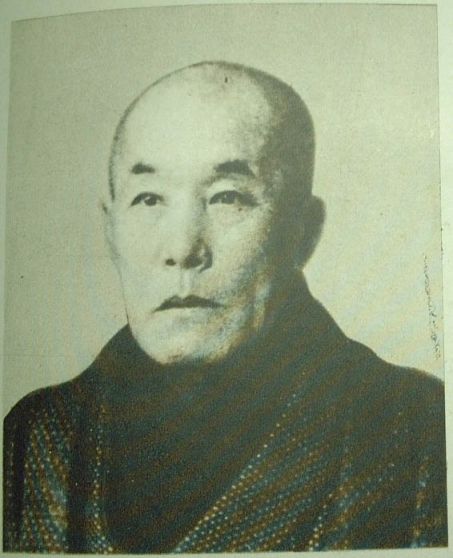 本名を西田伝助といい、「霞亭乙湖(かてい おとこ)」とも称した。浅草御蔵前瓦町生まれ、父は札差の板倉屋林右衛門である。天保改革で家は没落した。幕末期には「鼓汀」、明治になって、「菫坡」などの俳号を用いた。銀座役人辻伝右衛門が経営していた元大阪町の本屋の番頭であった頃、戯作者の条野伝平、浮世絵師の落合芳幾らと知り合い、日報社を起こした。明治5年2月東京日日新聞を創刊した。新聞事業に尽くしたが、明治24年に日報社を辞した。かなりの院本を所有していて、歌舞伎にも明るかった。
本名を西田伝助といい、「霞亭乙湖(かてい おとこ)」とも称した。浅草御蔵前瓦町生まれ、父は札差の板倉屋林右衛門である。天保改革で家は没落した。幕末期には「鼓汀」、明治になって、「菫坡」などの俳号を用いた。銀座役人辻伝右衛門が経営していた元大阪町の本屋の番頭であった頃、戯作者の条野伝平、浮世絵師の落合芳幾らと知り合い、日報社を起こした。明治5年2月東京日日新聞を創刊した。新聞事業に尽くしたが、明治24年に日報社を辞した。かなりの院本を所有していて、歌舞伎にも明るかった。東京日日新聞885号に署名記事(「霞亭乙湖」)が載っている。(爺の浮気相手を母娘が敵討ちの図)

青年綺堂とは、綺堂が東京日日新聞勤務で、菫坡老人がやまと新聞に関係していて、東京日日新聞社の印刷部の監督でもあったときに出会っている。歌舞伎座の創設者の一人で持主でもある、千葉勝五郎の縁者であったという。江戸時代のことや芝居のことなど、抜群の記憶力であったと、綺堂は書いている。また、菫坡老人が所有する義太夫の丸本が300余種あったが、そのうち200種あまりを貸してもらって読んだという。岡本綺堂・明治の演劇121頁以下(大東選書、1942)参照。
明治23年頃と思われる。綺堂が東京日日に就職して、1年ばかり経った頃である。綺堂は用事で、社の印刷部へ出かけた。そこには「やまと新聞」の西田菫坡翁がいた。やまと新聞の印刷も兼ねており、また同社の創立メンバーの一人でもあるためか、日日新聞社の一室が与えられていたようだ。
菫坡 「近頃、劇評をお書きになすッておられるのは、貴君(あなた)ですかい」
綺堂 「はい、そうです」
菫坡 「お手隙のときは、ここへちっと遊びにおいでなさい」
綺堂 「はい」
これが機縁で、その後、午後になると給仕を遣わして、綺堂に声をかけた。菫坡老人は、小奇麗に片付けてある別室に控えていて、茶や菓子などをご馳走した上に色々の芝居の話をしてくれた。
- 「それにしても、この人はどうして斯んなに芝居のことを能く知ってみるのであらうと、私は実に驚嘆した。最近の明治時代の事どもは勿論であるが、遠い江戸時代に遡って殆ど何でも知らないことは無いと云っていゝ位であった。狂言の事、俳優の事、それを極めて明細に年月日までを一々挙げて説明されるには、わたしも呆れて唯ぼんやりしている位で、その博識におどろくと共に、その記憶力の絶倫なるに私は胆を挫がれてしまった。かういふ始末で、初めは唯ぼんやりと口を明いていた私も、その後たび/\其別室へ呼ばれて、だん/\その話を聴かされるに連れて、眼の先が少しは明るくなったやうにも感じられた。」 ――岡本綺堂、明治の演劇122−23頁)。
西田菫坡がどういう人か興味があるが、その作品をはじめとしてほとんど触れる機会がないので、やっと見つけたインタビュー(聞取り話)をつぎに紹介します。この部分は、左團次(初世)が著名になる前の苦労話で、しかもそれが黙阿弥の直話の形をとっています。当時の会話の雰囲気とともに……。
○西田菫坡君談「團十郎と左團次」伊原敏郎(青々園)=後藤寅之助・編『唾玉集』(春陽堂、明治39.9)389‐391頁より。
- 「(黙阿弥は)……終(つひ)に市村座を暇(いとま)を取ツて仕舞ツた、それから此間死んだ守田(勘彌)の処へ来て、『私は市村座を出たから貴君(あなた)の処(とこ)へ使ツて下さいませんか』てえと『結構です、早速お出でなさい』『だが別にお頼(たのみ)があります、といふものは私に荷物が付いて居ますから、其れも買ツて下さい』といふから守田は『其の荷物てえのは左團次の事ツたらう、宜(よ)うがす、お連れなさいまし』と快く引受けて、黙阿彌も左團次も守田座に出るやうに成ツた。
是れから、成るたけ左團次の柄(がら)に適(は)まるやうな役を黙阿彌(かはたけ)が付けるやうに成ツて、段々出世した、尤も黙阿弥(かはたけ)ばかりで無い、例の婆さん中々(なか/\)丹精して確(しつ)かりしたもんで、『好色敷島物語』の時に左團次が源四郎坊主の役をしました、其の時書抜(かきぬき)の中(うち)に『葛籠(つゞら)の札を引剥(ひつぺ)がし』てえ台辞(せりふ)があるのを、『ひつぺがし』が如何(どう)しても言へない、『へつぺがし』と言ふんで、処(ところ)が婆(ばあ)さん側(そば)に付いて『べら坊め、へつぺがしてえ奴があるもんか』と小言が酷(ひど)いので、自分の前で度々(たび/\)言はせて台辞の稽古をさせ、とう/\最終(しまひ)に『ひつぺがし』と言へるやうに成ツた、其のうちに『樟紀流花見幕張(くすのきりうはなみのまくはり)』ですかな、忠彌です、あれから売り出して来て、所謂(いはゆる)盲見物(めくらけんぶつ)には先(ま)ア『團菊左(だんきくさ)』と言はれるやうに成ツて、全く黙阿彌(かはたけ)、お母(ふくろ)、守田の引立(ひきたて)が一致して今の身分に成ツたんですな、此奴(こいつ)が黙阿彌(もくあみ)の直話(ぢきわ)なんてす、黙阿彌てえのが中々(なか/\)他人の事を拵(こしら)えて言ふ人では無いのてす、況(ま)して左團次は子分(こぶん)ですから、……此の次が『天草』の狂言で、それで焼けました。……」
(注=全ルビを省略したところがあります)
明治25年になると、東京日日新聞社の経営は、関直彦の手から、伊東巳代治の手に移り、それに伴い、西田菫坡翁も社を去ったので、銀座にある翁の自宅を訪問する以外は、しだいに足が遠のいたという。
師とは言わないまでも、綺堂にとって重要な機会を作り出した、“恩人”たちとして、私は、つぎの3人を挙げるべきであろうと思う 。東京日日の社長でもあり、劇作の先輩でもあった福地桜痴(源一郎)、東京日日の社長で、綺堂少年を採用した関直彦、それに、綺堂デビューを実現した、壮士芝居・新派劇の川上音二郎である。
◆福地桜痴 (1841〜1906)
 長崎の人。本名源一郎。文久元年遣欧使節に随行して渡欧した。帰朝して、明治元年「江湖新聞」を発行した。西南の役のルポで頭角を現し、国民的人気を誇った。
長崎の人。本名源一郎。文久元年遣欧使節に随行して渡欧した。帰朝して、明治元年「江湖新聞」を発行した。西南の役のルポで頭角を現し、国民的人気を誇った。新聞言論人として有名で、東京日日新聞社の主筆、のちに社長として、政府系の論陣を張った。はじめて東京日日で「社説欄」を設けた。「池の端の御前(先生)」とも綽名されたが、かならず定刻に出勤し、下戸でもあり、厳格だったようだ。当時朝野新聞の成島柳北(旧幕府の奥儒者)との文章論争は有名で、成島の文章の詩趣・妙味に対して、福地は実用・達意主義を主張したという。
また、明治22年の歌舞伎座の設立に尽力するとともに、歌舞伎の作家としても活躍した。市川団十郎(9世)は、演劇の改良にも熱心で、歌舞伎関係者以外の、自分のブレーンともいえる求古会を組織して、いわば有職故実を研究して、歌舞伎に生かそうとしていた。漢学者の依田学海の脚本で、活歴ものをやった時期もあったが、学海とのつながりはうまくいかなかった。その後、団十郎は、桜痴の脚本で演じた。団十郎と桜痴の連携が成ったのである。
綺堂の父・純は、求古会を通じて、やはり会員であった桜痴と知り合ったと思われる。綺堂少年は、桜痴の紹介で、9世団十郎と歌舞伎座で会って、戯作者とならないかと誘われている。
また、桜痴の弟子である榎本虎彦(破笠)とは歳も近く、彼の紹介で、綺堂は築地の桜痴の自宅を訪問したりして、劇作を見てもらおうとしていた。榎本は、ポスト桜痴として、歌舞伎座付きの作者となって活躍した。
◆関 直彦
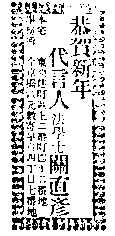
 紀州の出身。福地桜痴の後、若くして東京日日新聞社社長となる。明治25年に東日報社を辞し、弁護士として、さらには帝国議会議員として活躍した。東京帝大出身で、鳩山和夫門下でもあった関係で、桜痴と鳩山教授が知り合いで、英語のできる記者を探していたことから、東京日日入りが決まったようだ。
紀州の出身。福地桜痴の後、若くして東京日日新聞社社長となる。明治25年に東日報社を辞し、弁護士として、さらには帝国議会議員として活躍した。東京帝大出身で、鳩山和夫門下でもあった関係で、桜痴と鳩山教授が知り合いで、英語のできる記者を探していたことから、東京日日入りが決まったようだ。東京日日時代は、麹町に住んでおり、また綺堂の父の純と、求古会会員(メンバー)であったことから知己を得たようだ。父純の勧めで、綺堂は関宅に単身、面会と挨拶に行く。これによって、芝居作家志望であることを告げ、東京日日への就職が決まった。綺堂少年は、芝居を見ることができて、生活が成り立つという、一挙両得ということで大喜びだった。
綺堂が安定した経済生活で歌舞伎を見物し、研究でき、文筆で生活するという礎を築いたという意味で、功績があったといえる。綺堂少年は、東京日日への就職が決まる前は、自分の将来について父がなんともしてくれないと嘆いていたが、父・純(きよし)が持っていた東京日日ラインの桜痴と関直彦との関係は大きかったといえる。父のこのラインは、その江戸風流人としての面が実際に役に立ったのであった。周知のように、旧幕臣の子弟の官途への就職は、当時の藩閥政治を考えれば、綺堂本人も語るように非現実的な選択である。そこで、大学への進学あるいは漠然と学者として身を立てることを考えていたようであったが、父の連帯保証での経済的苦境があったため、実現しにくかった事情がこの前にある。
・関 直彦、七十七年の回顧 (昭和8年10月刊、三省堂)229頁には、つぎのように記している
- 「文士には、榎本破笠、岡本綺堂の両君あり、何れも青年時代には、余を頼りて斯界にはいりし人々なるが、両君共に劇界作家の雄、破笠は既に逝きたれども、綺堂は今猶絢爛たる花を舞台に咲かせつゝあり。」
◆川上音二郎 (1864−1911)
 新派俳優、興行師。福岡県博多・中対馬小路(なか・つましょうじ)の問屋の息子。巡査を辞め、自由党に入り自由民権運動に参加するが、「自由童子」と名乗るなどしたが、「過激の政談をしたる為」30数回におよぶ投獄。のち講釈師、さらに落語家に転じ、「浮世亭○○(まるまる)」と名のり、大阪で芝居を勉強した。書生芝居、壮士芝居、オッペケペー節で有名。劇団を組織して、川上座、帝国女優養成所、帝国座を創設した。正劇(翻訳劇)運動を続けて、国内外にも巡業して、新派劇発展の基礎を固めた。
新派俳優、興行師。福岡県博多・中対馬小路(なか・つましょうじ)の問屋の息子。巡査を辞め、自由党に入り自由民権運動に参加するが、「自由童子」と名乗るなどしたが、「過激の政談をしたる為」30数回におよぶ投獄。のち講釈師、さらに落語家に転じ、「浮世亭○○(まるまる)」と名のり、大阪で芝居を勉強した。書生芝居、壮士芝居、オッペケペー節で有名。劇団を組織して、川上座、帝国女優養成所、帝国座を創設した。正劇(翻訳劇)運動を続けて、国内外にも巡業して、新派劇発展の基礎を固めた。綺堂自身は、川上を毛嫌いし、その壮士芝居・書生芝居を軽蔑していたが、皮肉にも、明治41年7月、川上自身からの戯曲依頼で、芝居作家として著名になるきっかけを作ってもらうことになった。「維新前後」がそれで、綺堂は、きっと市川左団次(2世)が出るのかと念を押して、出るのならば……として、この作品を書いたのである。
2世左団次の苦境を救おうとして、「革新劇興行第一軍」(旧劇を担当)を組織し、川上がそのための脚本家として綺堂に眼をつけたところに、川上の先見の明と時代の回転がある。川上音二郎は、それまであまり作品が演じられたことのない綺堂を一躍劇作家に上らせた立役者といってよい。
綺堂は、川上の芝居はともかく、その興行師や新派の芝居の進め方や運営など、歌舞伎芝居を革新する面では一目を置くにいたったと述懐している。

「佐賀暴動記」川上音二郎 藤沢浅二郎 青柳捨三郎 (小林幾英・画)
明治24年の川上一座の東上後、明治25年正月・鳥越座での興行
話は前後するが、綺堂は、川上の東京での2回目の芝居を、明治24年7月に、鳥越座(中村座)ではじめて見物している。招待であったという。1番目が「拾遺後日連枝楠」(依田学海作)で、ついで「経国美談」(矢野龍渓作)、「佐賀暴動記」(久保田彦作)。1番目と2番目の間で、川上は「オッペケペー節」を歌ったという。
綺堂は、川上音二郎らの壮士芝居をつぎのように見ている。
- 「その当時、東京人からは一種軽蔑の眼を以て迎えられてゐた壮士芝居にその舞台を貸したのも、一種の苦し紛れであったらしい。併し兎もかくも大劇場である。東京の真中の大劇場へ乗り出して、一挙にその運命を決しようと企てた川上音二郎はたしかに大胆なる冒険家であった。」(岡本綺堂・明治の演劇131頁)
「川上の芝居を激烈に攻撃して、こんな芝居を喜んで見物してゐる人間があるのを悲しむ」
というようなことを書いたが、かえって川上芝居の人気に拍車をかける結果になったと述べている。岡本綺堂・明治の演劇135頁。
