つぎは、綺堂のオリジナル作品をデジタル化したものです。「青蛙神」は『青蛙堂鬼談』シリーズの第1話です。
なお、入力者自身による校正はいたしましたが、ベーター版ですので誤字などありましたら、ご連絡ください。
◆青蛙神 ――『青蛙堂鬼談』より
-
岡本綺堂
一
「速達!」
三月三日の午ごろに一通の速達郵便がわたしの家の玄関に投げ込まれた。
拝啓。春雪霏々、このゆうべに一会なかるべけんやと拝じ候。万障を排して、本日午後五時頃より御参会くだされ度、ほかにも五六名の同席者あるべくと存じ候。但し例の俳句会には無之候。まずは右御案内まで、早々、不一。
三月三日朝
青蛙堂主人
話の順序として、先ずこの差出人の青蛙堂《せいあどう》主人について少しく語らなければならない。井の中の蛙という意味で、井蛙《せいあ》と号する人はめずらしくないが、青いという字を冠《かぶ》らせた青蛙《せいあ》の号はすくないらしい。彼は本姓を梅沢君と云って、年はもう四十を五つ六つも越えているが、非常に気の若い、元気のいゝ男である。その職業は弁護士であるが、十年ほど前から法律事務所の看板を外してしまって、今では日本橋辺のある大商店の顧問という格で納まっている。ほかにも三四の会社に関係して、相談役とか監査役とかいう肩書を所持している。先ずは一廉《かど》の当世紳士である。梅沢君は若いときから俳句の趣味があったが、七八年前からいよくその趣味が深くなって、忙しい閑をぬすんで所々の句会へも出席する。自宅でも句会をひらく。俳句の雅号を金華と称して、あっぱれの宗匠顔をしているのである。
梅沢君は四五年前に、支那から帰った人のみやげとして広東製の竹細工を貰った。それは日本では迚《とて》も見られないような巨大な竹の根をくりぬいて、一匹の大きい蝦蟆《がま》をこしらえたものであるが、その蝦蟆は鼎《かなえ》のような三本足であった。一本の足はあやまって折れたのではない、初めから三本の足であるべく作られたものに相違ないので、梅沢君も不思議に思った。呉れた人にもその訳はわからなかった。いずれにしても面白いものだというので、梅沢君はその蝦蟆を座敷の床の間に這わせて置くと、ある支那通の人が教えてくれた。
「それは普通の蝦蟆ではない。青蛙というものだ。」
その人は清《しん》の阮葵生《げんきせい》の書いた「茶余客話《ちやよかくわ》」という書物を持って来て、梅沢君に説明して聞かせた。それには斯ういうことが漢文で書いてあった。
――杭州に金華将軍なるものあり。蓋し青蛙の二字の訛りにして、その物はきわめて蛙に類す。但だ三足なるのみ。そのあらわるゝは、多く夏秋の交《こう》にあり。降《くだ》るところの家は※[#禾編+朮]酒《じゆつしゆ》一盂を以てし、その一方を欠いてこれを祀る。その物その傍らに盤踞して飲み咬《くら》わず、而もその皮膚はおのずから青より黄となり、更に赤となる。祀るものは将軍すでに酔えりといい、それを盤にのせて湧金門外の金華太侯の廟内に送れば、たちまちにその姿を見うしなう。而して、その家は数日の中にかならず獲《う》るところあり。云々《しか/″\》――。[#ここまで1コマおち]
これで三本足の蝦蟆の由来はわかった。それのみならず、更に梅沢君をよろこばせたのは、その霊ある蝦蟆が金華将軍と呼ばれることであった。梅沢君の俳号を金華というのに、恰もそこへ金華将軍の青蛙が這い込んで来たのは、まことに不思議な因縁であるというので、梅沢君はその以来大いにこの蝦蟆を珍重することになって、ある書家にたのんで青蛙堂という額を書いて貰った。自分自身も青蛙堂主人と号するようになった。
その青蛙堂からの案内をうけて、わたしは躊躇した。案内状にも書いてある通り、きょうは朝から細い雪が降っている。主人はこの雪をみて俄に今夜の会合を思い立ったのであろうが、青蛙堂は小石川の切支丹坂をのぼって、昼でも薄暗いような木立の奥にある。こういう日のゆう方からそこへ出かけるのは、往きは兎もあれ、復《かえ》りが難儀だと少し恐れたからである。例の俳句会ならば無論に欠席するのであるが、それではないと態々《わざ/\》断り書きがしてある以上、何かほかに趣向があるのかも知れない。三月三日でも梅沢君に雛祭をするような女の子はない。まさかに桜田浪士の追悼会を催すわけでもあるまい。そんなことを考えているうちに、好い塩梅に雪も小降りになって来たらしいので、わたしは思い切って出かけることにした。
午後四時頃からそろ/\と出る支度をはじめると、あいにくに雪は又はげしく降り出して来た。その景色を見てわたしは又躊躇したが、えゝ構わずにゆけと度胸を据えて、とう/\真白な道を踏んで出た。小石川の竹早町で電車にわかれて、藤坂を降りる、切支丹坂をのぼる、この雪の日には可なりに難儀な道中をつゞけて、兎もかくも青蛙堂まで無事にたどり着くと、もう七八人の先客があつまっていた。
「それでも皆んな偉いよ。この天気にこの場所じゃあ、せいぜい五六人だろうと思っていたところが、もう七八人も来ている。まだ四五人は来るらしい。どうも案外の盛会になったよ。」と、青蛙堂主人はひどく嬉しそうな顔をして私を迎えた。
二階へ案内されて、十畳と八畳をぶちぬきの座敷へ通されて、さて先客の人々を見わたすと、そのなかの三人ほどを除いては、みな私の見識らない人達ばかりであった。学者らしい人もいる。実業家らしい人もいる。切髪《きりかみ》の上品なお婆さんもいた。そうこう思うと、まだ若い学生のような人もいた。なんだか得体《えたい》のわからない会合であると思いながら、先ず一通りの挨拶をして座に着いて、顔なじみの人たちと二つ三つの世間話などをしているうちに、私のあとから又二三人の客が来た。そのひとりは識っている人であったが、ほかの二人はどこの何という人だが判らなかった。
やがて主人からこの天気に好うこそと云うような挨拶があって、それから一座の人々を順々に紹介した。それが済んで、酒が出る、料理の膳が出る。雪はすこし衰えたが、それでも休みなしに白い影を飛ばしているのが、二階の硝子戸越しに窺われた。あまりに酒を好む人がないとみえて、酒宴は案外に早く片附いて、更に下座敷の広間へ案内されて、煙草を喫《す》って、あついレモン茶を啜《すゝ》って、しばらく休息していると、主人は勿体らしく咳《しわぶ》きして一同に声をかけた。
「実はこのような晩にわざ/\お越しを願いましたのは外でもございません。近頃わたくしは俳句以外、怪談に興味を持ちまして、ひそかに研究しております。就きましては一夕怪談会を催しまして、皆さまの御高話を是非拝聴いたしたいと存じて居りましたところ、恰も今日は春の雪、怪談には雨の夜の方がふさわしいかと存じましたが、雪の宵もまた興あることゝ考えまして、急に思いついてお呼び立て申したような次第でございます。わたくしばかりでなく、これにも聴き手が控えておりますから、どうか皆さまに、一席ずつ珍しいお話をねがいたいと存しますが、如何でございましょうか。」
主人が指さす床の間の正面には、彼の竹細工の三本足の蝦蟆が大きくうずくまっていて、その前には支那焼らしい酒壷が供えてある。欄間には青蛙堂と大きく書いた額がかゝっている。主人のほかに、この青蛙を聴き手として、われ/\はこれから怪談を一席ずつ弁じなければならないことになったのである。雛祭の夜に怪談会を催すも変っているが、その聴き手には三本足の金華将軍が控えているなどは、いよ/\奇抜である。主人の注文に対して、どの人も無言のうちに承諾の色目《いろめ》をみせたが、さて自分から先ず進んでその皮切りを勤めようという者もない。たがいに顔をみあわせて譲り合っているような形であるので、主人の方から催促するように第一番に出る人を指名することになった。
「星崎さん。いかゞでしょう。あなたから先ず何かお話し下さらるわけには……。この青蛙をわたくしに教えて下すったのは貴方《あなた》ですから、その御縁であなたから先ず願いましょう。今晩は特殊の催しですから、そういう材料を沢山お持ちあわせの方々ばかりを選んでお招き申したのですが、誰か一番に口を切る方がないと、やはり遠慮勝になってお話が進行しませんようですから。」
真先に引き出された星崎さんというのは、五十ぐらいの紳士である。かれは薄白くなっている髭をなでながら微笑した。
「なるほどそう云われると、この床の間の置物にはわたしが縁のふかい方かも知れません。わたしは商売の都合で、若いときには五年ほども上海の支店に勤めていたことがあります。その後にも二年に一度、三年に一度ぐらいは必ず支那へゆくことがあるので、支那の南北は大抵遍歴しました。そういうわけで支那の事情もすこしは知っています。御主人が唯今おっしやった通り、その青蛙の説明をいたしたのも私です。」
「それですから、今夜のお話はどうしてもあなたからお始めください。」と、主人はかさねて促した。
「では、皆さまを差措いて、失礼ながら私が前座を勤めることにしましょう。一体この青蛙に対する伝説は杭州地方ばかりでなく、広東地方でも青蛙神と云って尊崇しているようです。したがって、昔から青蛙については色々の伝説が残っています。勿論その多くは怪談ですから、丁度今夜の席上には相応しいかも知れません。その伝説のなかでも成るべく風変りのものを鳥渡《ちよつと》お話し申しましょう。」
星崎さんは一膝ゆすり出て、先ず一座の人々の顔をしずかに見まわした。その態度がよほど場馴れているらしいので、わたしも一種の興味をそゝられて、思わずその人の方にむき直った。
二
支那の地名や人名は皆さんにお馴染が薄くて、却って話の興をそぐかと思いますから、なるべく固有名詞は省略して申上げることにしましょう。と、星崎さんは劈頭に先ず断った。
時代は明《みん》の末で、天下が大いに乱れんとする時のお話だと思ってください。江南の金陵、すなわち南京の城内に張訓という武士があった。ある時、その城をあずかっている将軍が饗宴をひらいて列席の武官と文官一同に詩や絵や文章を自筆でかいた扇子一本ずつをくれた。一同ひどく有難がって、めい/\に披《ひら》いてみる。張訓もおなじく押頂いて披いてみると、どうしたわけか自分の貰った扇だけは白扇で、なにも書いてない。裏にも表にも無い。これには甚だ失望したが、この場合、上役の人に対して、それを云うのも礼を失うと思ったので、張訓はなにげなくお礼を申して、ほかの人たちと一緒に退出した。しかし何だか面白くないので、家へ帰るとすぐに其妻に話した。
「将軍も一度に沢山の扇をかいたので、屹《きつ》と書き落したに相違ない。それが生憎におれに当ったのだ。とんだ貧乏鬮《くじ》をひいたものだ。」
詰らなそうに溜息をついていると、妻も一旦は顔の色を陰《くも》らせた。妻は今年十九で三年前から張と夫婦になったもので、小作りで色の白い、右の眉のはずれに大きい黒子《ほくろ》のある、まことに可愛らしい女であったが、夫の話をきいて少し考えているうちに、又だん/\にいつもの晴れやかな可愛らしい顔に戻って、かれは夫を慰めるように云った。
「それはあなたの仰《おつ》しゃる通り、将軍は別に悪意《わるぎ》があってなされた事ではなく、沢山のなかですから、屹とお書き落しになったに相違ありません。あとで気がつけば取換えて下さるでしょう。いゝえ、きっと取換えて下さいます。」
「しかし気がつくかしら。」
「なにかの機《はずみ》に思い出すことがないとも限りません。それについて、若し将軍から何かお尋ねでもありましたら、そのときには遠慮なく、正直にお答えをなさる方がようございます。」
「むゝ。」
夫は気のない返事をして、その晩は先ずそのまゝで寝てしまった。それから二日ほど経つと、張訓は将軍の前によび出された。 「おい。このあいだの晩、おまへに遣った扇には何が書いてあったな。」
こう訊かれて、張訓は正直に答えた。
「実は頂戴の扇面には何にも書いてございませんでした。」
「なにも書いてない。」と、将軍はしばらく考えていたが、やがて、徐《しずか》かに首肯《うなず》いた。
「なるほど、そうだつたかも知れない。それは気の毒なことをした。では、その代りにこれを上げよう。」
前に貰ったのよりも遼かに上等な扇子に、将軍が手ずから七言絶句を書いたのを呉れたので、張訓はよろこんで頂戴して帰って、自慢らしく妻にみせると、妻もおなじように喜んだ。
「それだから、わたくしが云ったのです。将軍はなか/\物覚えのいゝ方ですから。」
「そうだ、まったく物覚えが好い。大勢のなかで、どうして白扇がおれの手に這入ったことを知っていたのかな。」
そうは云っても、別に深く穿鑿するほどのことではないので、それは先ずそのまゝで済んでしまった。それから半年ほど経つと、彼の闖賊《ちんぞく》という怖ろしい賊軍が蜂起して、江北は大いに乱れて来たので、南方でも警戒しなければならない。太平が久しくつゞいて、誰も武具の用意が十分であるまいと云うので、将軍から部下の者一同に鎧一着ずつを分配してくれることになった。張訓もその分配をうけたが、その鎧がまた悪い。古い鎧で破れている。それをかゝえて、家へ帰って、又もや妻に愚痴をこぼした。
「こんなものが、大事のときの役に立つものか。いっそ紙の鎧を着た方がましだ。」
すると、妻はまた慰めるように云った。
「それは将軍が一々にあらためて渡したわけでもないのでしょうから、あとで気がつけば屹と取換えて下さるでしょう。」
「そうかも知れないな。いつかの扇子の例もあるから。」
そう云っていると、果して二三日の後に、張訓は将軍のまえに呼び出されて、この間の鎧はどうであったかと、又訊かれた。張訓はやはり正直に答えると、将軍は仔細ありげに眉をよせて、張の顔をじっと眺めていたが、やがて詞《ことば》をあらためて訊いた。
「おまえの家《うち》では何かの神を祭っているか。」
「いえ、一向に不信心でございまして、なんの神仏《かみほとけ》も祭って居りません。」
「どうも不思議だな。」
将軍の額の皺はいよ/\深くなった。そのうちに何を思い付いたのか、かれは又訊いた。
「おまえの妻はどんな女だ。」
突然の問に、張訓はいさゝか面喰ったが、これは隠すべき筋でもないので、正直に自分の妻の年頃や人相などを申立てると、将軍は更にきいた。
「そうして、右の眉の下に大きな黒子《ほくろ》はないか。」
「よく御存じで……。」と、張訓もおどろいた。
「むゝ、知っている。」と、将軍は大きく首肯《うなず》いた。「おまえの妻はこれまで、二度もおれの枕もとへ来た。」
驚いて、呆れて、張訓はしばらく相手の顔をぼんやりと見つめていると、将軍も不思議そうにその仔細を説明して聞かせた。
「実は半年ほど前に、おまえ達を呼んでおれの扇子を遣ったことがある。その明くる晩のことだ。ひとりの女がおれの枕もとへ来て、昨日張訓に下さいました扇子は白扇でございました。どうぞ御直筆のものと御取換えをねがいますと、云うかと思うと夢がさめた。そこで、念のためにお前をよんで訊いてみると、果してその通りだという。そのときにも少し不思議に思ったが、まず其儘にして置くと、又ぞろその女がゆうべも来て、先日張訓に下さいました鎧は、朽ち破れていて物の用にも立ちません。どうぞ然るべき品と御取換えをねがいますと云う。そこで、おまえに訊いてみると、今度も又その通りだ。あまりに不思議がつゞくので、もしやと思って詮議すると、その女は正しくお前の妻だ。年ごろと云い、人相といい、眉の下の黒子までが寸分違わないのだから、もう疑う余地はない。おまえの妻は一体どういう人間だか知らないが、どうも不思議だな。」
仔細をきいて、張訓もいよ/\呆れた。
「まったく不思議でございます。よく詮議をいたしてみましょう。」
「いずれにしても鎧は換えてやる。これを持ってゆけ。」将軍から立派な鎧をわたされて、張訓はそれをかゝえて退出したが、頭はぼんやりして半分は夢のような心持であった。三年越し連れ添って、なんの変ったこともない貞淑な妻が、どうしてそんなことをしたのか。さりとて将軍の詞《ことば》に嘘があろうとは思われない。家へ帰る途中で色々かんがえてみると、なるほど思い当ることがある。半年前の扇子の時にも、今度の鎧の問題にも、妻はいつでも先を見越したようなことを云って自分を慰めてくれる。それがどうも可怪《おか》しい。たしかに不思議だ。これは一と詮議しなければならないと、張訓は急いで帰ってくると、妻はその鎧を眼疾《ばや》く見つけてにっこり[#「にっこり」に傍点]笑った。
その可愛らしい笑い顔は鬼とも魔とも変化《へんげ》とも見えないので、張訓はまた迷った。しかし彼のうたがいはまだ解けない。殊に将軍の手前に対しても、なんとかこの解決を付けなければならないと思ったので、かれは妻を一間《ま》へ呼び込んで、先ずその夢の一条を話すと、妻も不思譲そうな顔をして聞いていた。そうして、こんなことを云った。
「いつかの扇子のときも、今度の鎧についても、あなたは大層心もちを悪くしておいでのようでしたから、どうかしてお心持の直るようにして上げたいと、わたくしも心から念じていました。その真心が天に通じて、自然にそんな不思議があらわれたのかも知れません。わたくしも自分の念がとゞいて嬉しゆうございます。」
そう云われてみると、夫もその上に踏み込んで詮議の仕様もない。唯わが妻のまごころを感謝するのほかはないので、結局,その場は有耶無耶に済んでしまったが、張訓はどうも気が済まない。その後も注意して妻の挙動《そぶり》をうかゞっているうちに、前にも云う通りのわけで世の中はだん/\騒がしくなる。将軍も軍務に忙しいので、張訓の妻のことなどを詮議してもいられなくなった。張訓もまた自分の務が忙しいので、朝は早く出て、夕《ゆうべ》はおそく帰る。こうして半月あまりを暮していると、五月に這入って梅雨が毎日ふり続く。それも今日《きよう》はめずらしくや午後から小歇《や》みになって、夕方には薄青い空の色がみえて来た。
張訓も今日はめずらしく自分の仕事が早く片附いて、まだ日の暮れ切らないうちに帰ってくると、いつもはすぐに出迎えをする妻がどうしてか姿を見せない。内へ這入って庭の方を不図みると、庭の隅には大きい柘榴《ざくろ》の木があって、その花は火の燃えるように紅く咲きみだれている。妻はその花の蔭に身をかゞめて、なにか一心にながめているらしいので、張訓は竊《そつ》と庭に降り立って、ぬき足をして妻のうしろに近寄ると、柘榴の木のが下には大きい蝦蟆《がま》が傲然としてうずくまっている。その前に酒壷をそなえて、妻は何事をか念じているらしい。張訓はこの奇怪なありさまに胸をとゞろかして猶も注意して窺うと、その蝦蟆は青い苔のような色をして、しかも三本足であった。
それが例の青蛙であることを知っていたら、何事もなしに済んだかも知れなかったが、張訓は武人で、青蛙神も金華将軍もなんにも知らなかった。かれの眼に映ったのは、自分の妻が奇怪な三本足の蝦蟆を拝している姿だけである。このあいだからの疑いが初めて解けたような心持で、かれは忽ちに自分の剣をぬいたかと思うと、若い妻は背中から胸を突き透されて、殆ど声を立てる間もなしに柘榴の木の下に倒れた。その死骸の上に紅い花がはら/\と散った。
張訓はしばらく夢のように突っ立っていたが、やがて気がついて見まわすと、三本足の蝦蟆はどこへか影を隠してしまって、自分の足もとに転げているのは妻の死骸ばかりである。それをじっと眺めているうちに、かれは自分の短慮を悔むような気にもなった。妻の挙動《そぶり》は確に奇怪なものに相違なかったが、兎もかくも一応の詮議をした上で、生かすとも殺すとも相当の処置を取るべきであったのに、一途に※[#しんにゅう編+「端」の立編を除いた字]《はや》まって成敗してしまったのはあまりに短慮であったとも思われた。しかし今更どうにもならないので、かれは妻のなきがらの始末をして、翌日それを竊《ひそ》かに将軍に報告すると、将軍はうなずいた。
「おまえの妻は矢はり一種の鬼であったのだ。」
三
それから張訓の周囲には色々の奇怪な出来事が続いてあらわれた。かれの周囲にはかならず三本足の蝦蟆が附きまとっているのである。室内にいれば、その榻《とう》のそばに這っている。庭に出れば、その足もとに這って来る。外へ出れば、矢はりそのあとから附いてくる。あたかも影の形にしたがうが如きありさまで、どこへ行っても彼のある所にはかならず青い蝦蟆のすがたを見ないことはない。それも最初は一匹であったが、後には二匹となり、三匹となり、五匹となり、十匹となり、大きいのもあれば小さいのもある。それがそろ/\繋がって、かれのあとを附けまわすので、張訓も持てあました。
その怪しい蝦蟆の群は、かれに対して別に何事をするのでもない。唯のそ/\と附いて来るだけのことであるが、何分にも気味がよくない。勿論、それは張訓の眼にみえるだけで、ほかの者にはなんにも見えないのである。かれも堪らなくなって、とき/″\剣をぬいて斬り払おうとするが、一向に手堪《てごた》えがない。たゞ自分の前にいた蝦蟆がうしろに位置をかえ、左にいたのが右へ移るに過ぎないので、どうにも斯うにもそれを駆逐する方法がなかった。
そのうちに彼等は色々の仕事をはじめて来た。張訓が夜寝ていると、大きい蝦蟆がその胸のうえに這いあがって、息が止まるかと思うほどに強く押付けるのである。食卓にむかって飯を食おうとすると、小さい青い蝦蟆が無数にあらわれて、皿や椀のなかへ片端から飛び込むのである。それがために夜もおちおちは眠られず、飯も碌々には食えないので、張訓も次第に痩せおとろえて半病人のようになってしまった。それが人の目に立つようにもなったので、かれの親友の羊得というのが心配して、だん/\その事情を聞きたゞした上で、ある道士をたのんで祈祷を行って貰ったが、やはりその効《しるし》はみえないで、蝦蟆は絶えず張訓の周囲に附きまとっていた。
一方かの闖賊は勢います/\猖厥になって、都もやがて危いという悲報が続々来るので、忠節のあつい将軍は都へむけて一部隊の援兵を送ることになった。張訓もその部隊のうちに加えられた。病気を申立てゝ辞退したらよかろうと、羊得は切《しき》りにすゝめたが、張訓は聞かずに出発することにした。かれは武人気質で報国の念が強いのと、もう一つには、得体も知れないも上蝦蟆の怪異に悩まされて、いたずらに死を侍つよりも帝城の下《もと》に忠義の死屍を横えた方が優《ま》しであるとも思ったからであった。かれは生きて再び還らない覚悟で、家のことなども残らず始末して出た。羊得も一緒に出発した。
その一隊は長江を渡って、北へ進んでゆく途中、ある小さい村落に泊まることになったが、人家が少ないので、大部分は野営した。柳の多い村で、張訓も羊得も柳の大樹の下に休息していると、初秋の月のひかりが鮮かに鎧の露を照らした。張訓の鎧はかれの妻が将軍の夢まくらに立って、とりかえて貰ったものである。そんなことを考えながらうっとりと月をみあげていると、傍《そば》にいる羊得が訊いた。
「どうだ。例の蝦蟆はまだ出て来るか。」
「いや、江を渡ってからは消えるように見えなくなった。」
「それは好《い》い塩梅だ。」と、羊得もよろこばしそうに云った。
「こっちの気が張っているので、妖怪も附け込む隙がなくなったのかも知れない。やっばり出陣した方がよかったな。」
そんなことを云っているうちに、張訓は俄に耳をかたむけた。
「あ、琵琶の音がきこえる。」
それが羊得には些《ちつ》ともきこえないので、大方おまえの空耳であろうと打消したが、張訓はどうしても間えると云い張った。 しかもそれは自分の妻の撥音《ばちおと》に相違ない。どうも不思議なこともあるものだと、かれはその琵琶の音にひかれるように、弓矢を捨てゝふら[#「ふら」に傍点]/\とあるき出した。羊得は不安に思って、あわてゝそのあとを追って行ったが、張の姿はもう見えなかった。
「これは唯事でないらしい。」
羊得は引返して三四人の朋輩を誘って、明るい月をたよりに其処らを尋ねあるくと、村を出たところに古い廟があった。あたりは秋草に掩われて、廟の軒も扉もおびたゞしく荒れ朽ちているのが月のひかりに明らかに見られた。虫の声は雨のようにきこえる。もしやと思って草むらを掻きわけて、その廟のまえまで辿りつくと、先に立っている羊得があっ[#「あっ」に傍点]と声をあげた。
廟の前には蝦蟆のような形をした大きい石が蟠《わだか》まっていて、その石の上に張訓の鎧が載せてあった。そればかりでなく、その石の下《もと》には一匹の大きい青い蝦蟆が恰もその兜を守るが如くにうずくまっているのを見たときに、人々は思わず立疎んだ。羊得はそれが三本足であるか何《ど》うかを確めようとする間もなく、蝦蟆のすがたは消えるように失せてしまった。人々は云い知れない恐怖に打たれて、しばらく顔を見あわせていたが、この上はどうしても廟内を詮素しなければならないので、羊得は思い切って扉をあけると、他の人々も怖々《こわ/″\》ながら続いて這入った。
張訓は廟のなかに冷たい体を横えて、眠ったように死んでいた。おどろいて介抱したが、かれはもうその眠りから醒めなかった。よんどころなくその死骸を運んで帰って、一体あの廟には何を祭ってあるのかと村のものに訊くと、単に青蛙神《せいあじん》の廟であると云い伝えられているばかりで、誰もその由来を知らなかった。廟内はまったく空虚で何物を祭ってあるらしい様子もなく、この土地でも近年は参詣する者もなく、たゞ荒れるがままに打捨てゝあるのだと云うことであった。青蛙神――それが何であるかを羊得等も知らなかったが、大勢の兵卒のうちに杭州出身の者があって、その説明によって初めて仔細が判った。張訓の妻が杭州生れであることは羊得も知っていた。
「これで、このお話はおしまいです。そういうわけですから、皆さんもこの青蛙神に十分故意を払って、怖るべき祟をうけないように御用心をねがいます。」
こう云い終って、星崎さんはハンカチーフで口のまわりを拭きながら、床の間の大きい蝦蟆をみかえった。
----------
底本:大衆文学大系7 岡本綺堂 菊池寛 久米正雄 集 昭和46年10月20日 第1刷 講談社
入力:和井府清十郎
公開日:2001年5月7日
※繰返しを意味する「二のつづけ字」のような字を「々」に改めた。
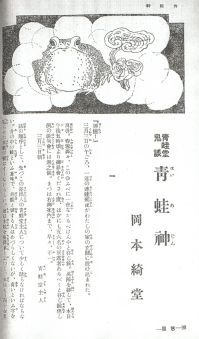
『苦楽』1925(大正14)年3月1日号98頁
